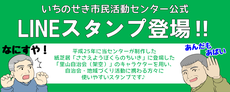(idea 2025年3月号掲載)※掲載当時と現在では情報が変わっている可能性があります。
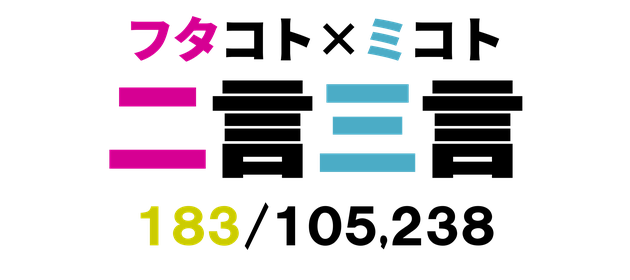
※お願い※
記事内の写真や資料は、当情報誌での使用について許可をいただいて掲載しております。
無断での転載などの二次利用はご遠慮ください。
「地域らしさ」を伝えて残す
~地元を出て気づいた「危機感」【後編】~
令和5年6月号から本誌の表紙写真を担当。写真は、東光山観福寺(一関市舞川)の観音堂にて、
本誌令和6年6月号の表紙写真を撮影する様子。
フォトグラファー 遠藤凌平
一関学院高等学校から東京農業大学へ進学。卒業後は秋田県内の企業へ就職し、フィリピンへの語学留学を経て、令和2年に地元へUターン。フリーランスのフォトグラファーとして地元で活動しながら、写真教室や情報発信ツールの講師依頼にも対応している。一関市室根町出身・在住。
対談者 フォトグラファー 遠藤凌平さん
聞き手 いちのせき市民活動センター センター長 小野寺浩樹
市内で写真撮影を生業とする企業や個人が多い中、写真教室で講師を務めるなど露出があり、地域から特に親しまれているフォトグラファーの遠藤さん。活動の背景には、地域をつくる根本である「地域らしさ」を残していきたいという想いがあり……。今回は、各地をまわって活動してきた目線から、地元・一関市の未来について考えます(2回シリーズの後編。前編はコチラ)。
小野寺 地元のアイデンティティが失われていく危機感から、「地域らしさ」という価値を発信・記録していく活動をしている、というお話がありました。
遠藤 はい。ただ、世間の大きな流れは変えられないと思っています。でも、残しておけば、またいつか復活できるかもしれないし、後からそれらの価値を再発見することができる。完全になくなってしまうと、復活できなくなってしまいますから。
小野寺 郷土芸能など、映像として記録していく流れになっていますよね。
遠藤 そうですね。永井地区郷土芸能伝承保存会から話を聞いたとき、「昔は娯楽としても親しまれていた」と教えてもらいましたが、現代は娯楽が選び放題ですし、「新しくてみんなが『良い』と言っているもの」に集約されていったのだと思います。伝統芸能は現代のものに比べたら地味に見えるかもしれませんが、見かけだけじゃなく、中身の方に良さがあると感じています。
小野寺 日本の伝統は、一つひとつに祈りや願いがありますからね。
遠藤 そういった「良さ」や「らしさ」を海外に行ってから初めて気づいて。時代を切り拓いてきた人たちがいるからこそ豊かな国になったわけですが、失ったものもあって……。現在、様々な原因から日本の経済が落ち込んできているという現実もあり、その危機を自分事として捉えていかないと、地方は特に早い段階で衰退していくと思います。大体の人は、なくなる直前になって「あぁ、○○ってなくなるんだ」と初めて気づきますよね。なくなる前に何とかしなきゃいけない。
小野寺 地域の力だけで、あれもこれも守って残すというのは難しくなってきましたよね。マンパワーがなくなってきたというか。
遠藤 それは地元に戻ってきたときに感じましたね。引き継いできたものを全部守ろうとして、みんな疲れ切っていたので、この状況はすごくまずいなと。当事者が疲れ切ってしまうとイベントなどの勢いもなくなり、「だったらもうやめよう」となってしまう。残された人たちがただ苦労して辛くなるだけにならないように、その人たちが報われるように支援ができればいいなと思っています。
小野寺 「室根神社祭のマツリバ行事(本誌令和6年11月号で紹介)」にしかり、「維持する」というのは想像以上に大変なことで、現在まで残してくれていることに感銘を受けます。
遠藤 これまで守ってきた「お祭り」「伝統芸能」「風習」などが、地元のアイデンティティであり、地元人のベースをつくっているのだと思うので、それを失くして、日本人の平均的な形だけが残るのは違うと考えています。一度倒れて(廃れて)しまったら、また起こすのに人や時間、お金がかかってしまうので、危機感を持ってほしい。
小野寺 いますぐに「地域らしさ」が出来上がるわけではなく、その地域が紡いできた歴史などが、その地域らしさをつくっているということですね。昔の人が続けてきた伝統には、生きている幸せを感じるための要素が強くありました。
遠藤 昔とは暮らし方が違って、「より豊かに生きていくにはどうすればいいか」を考えてしまう。「生きている幸せ」よりも上を求めてしまうから、苦しくなったり、何かがおかしくなったりするのだと思うんです。今は、ほとんど餓死もないし、「○歳までは死なない」と思っている人が多いですよね。1日1日を必死に生きていないから、「明日でいいや」と先延ばされていく。そうやって生きていくと、色んなものが知らないうちになくなっていきます。
小野寺 今の日本は生きていることが当たり前に感じる時代なので、祈りや願いの意味が薄くなり、伝統も形骸化し、廃れていったのかもしれません。
遠藤 地元から出なかったら気づかなかったことなので、一回地元を離れ、客観的に地元を見てみるのは大事だと思います。違う文化に触れると、当たり前が当たり前ではないと気づきますから。
小野寺 当センタースタッフもUターン就職が多く、遠藤さんと同じ経験をしています。
遠藤 無理やりに地元に残って就職するよう押し込めるんじゃなくて、外に出て行って色んな価値観や知識を吸収して戻って来てもらえば、より良いものがつくれると思うんです。地元を出て行った人が戻りたくなるまち、そして、残った人たちが損をしないまちにしなきゃいけない。
小野寺 「地元に戻りたい」という気持ちは、心の成長過程で生まれるのでしょうね。一関の暮らしの中の文化や根付いているものがあるからこそ、地元に懐かしさを感じ、守りたいという気持ちになっていくのかも。東京に行くと、地方の自慢大会とかやりますよね。
遠藤 あるあるですね(笑)。「おらほでこいづ作ってんだぞ!」って。
小野寺 そう、あれが日常的にできると良いですよね。身近にあるものが当たり前すぎて、特別に感じないのかもしれません。「一関といえば?」と聞かれたとき、市民のみなさんが「これ!」と自信満々に答えられるようになるといいですよね。
遠藤 一関市は「観光」や「移住・定住の支援」にも力を入れているかと思いますが、地元の人が「おらほに何もない」って言ってしまう状態なのは、外から来た人にマイナスな印象を与えてしまう。地域間の「垣根」を感じることも多々ありますが、今こそ市全体で連携していくべきだと考えています。
小野寺 「何もない」ではなくて、当たり前であることに価値を見出していきたいですよね。一関市を持続させていくために、改めて地元の価値を認識し、一人一人が後世に残すための努力をしていかなければいけません。
- idea 2025
- 過去の情報紙idea(PDFデータ)
- 団体紹介
- 地域紹介
- 企業紹介
- 博識杜のフクロウ博士
- センターの自由研究
- 二言三言
- 戸田さちえさん(前編)
- 遠藤凌平さん(後編)
- 遠藤凌平さん(前編)
- 菅原舞さん(後編)
- 菅原舞さん(前編)
- 鈴木英樹さん(後編)
- 鈴木英樹さん(前編)
- 宇津野泉さん(後編)
- 宇津野泉さん(前編)
- 一関市 市長公室 政策企画課 DX推進係(後編)
- 一関市 市長公室 政策企画課 DX推進係(前編)
- 一関市教育委員会 学校教育課(後編)
- 一関市教育委員会 学校教育課(前編)
- 塩竃一常さん(後編)
- 塩竃一常さん(前編)
- 塩竃一常さん(誌面こぼれ話)
- 皆川かおりさん
- 岩渕城光さん(後編)
- 岩渕城光さん(前編)
- 佐藤良平さん(後編)
- 佐藤良平さん(前編)
- 千田修一さん
- 小岩俊彦さん
- 芳賀修一さん
- 高橋昇禎さん 石川愛礼(後編)
- 高橋昇禎さん 石川愛礼(前編)
- 高橋勝男さん(後編)
- 高橋勝男さん(前編)
- 橋野智弘さん(後編)
- 橋野智弘さん(前編)
- 村上敬一さん
- 庄子幸華さん
- 那須浩修さん(後編)
- 那須浩修さん(前編)
- Aimi Bellさん 垣内幸治さん(後編)
- Aimi Bellさん 垣内幸治さん(前編)
- 小岩邦弘さん
- 木村正明さん(後編)
- 木村正明さん(前編)
- きくしんちゃんねる(後編)
- きくしんちゃんねる(前編)
- 近藤紀子さん・正信さん(後編)
- 近藤紀子さん・正信さん(前編)
- 伊藤公夫さん(後編)
- 伊藤公夫さん(前編)
- 山岸公美さん(後編)
- 山岸公美さん(前編)
- 岩本智子さん
- 野田隆弘さん (後編)
- 野田隆弘さん (前編)
- 水谷みさえさん、大林学さん(後編)
- 芦謙二さん、梁川真一さん(前編)
- 佐藤一伯さん(後編)
- 佐藤一伯さん(前編)
- 伊藤明さん
- 石田郁絵さん
- 岩井佳子さん(後編)
- 岩井佳子さん(前編)
- 千葉日出雄さん(後編)
- 千葉日出雄さん(前編)
- 佐久間渓雲さん
- 水木鶴升さん
- 千田寿美子さん
- 沼倉麻友さん
- 戸田仕さん
- 三浦幹夫さん
- 吉田真童さん
- 佐々木恭平さん
- 佐藤伸さん
- 菅原敏さん、佐藤夕子さん
- 佐藤好さん
- 加藤忍さん
- 小岩広昭さん
- 岩渕豊子さん
- 鈴木 英一さん
- 菅原 仁さん
- 黒澤真澄さん
- 伊藤稔さん
- 松岡俊太郎さん
- 菊地昌斉さん
- 中芝浩美さん
- 及川武芳さん
- 三浦勝利さん
- 清田博美さん
- 加藤鉄平さん
- 梁川真一さん
- 二言三言な人々
- 岩渕典仁さん
- 岩渕福美さん、佐藤友紀さん、岩渕城光さん
- 新井靖明さん
- 菅原順一さん
- 佐々木朋美さん、千葉エミさん、吉田ひろみさん
- 山川純一さん
- 工藤 正隆さん
- 伊藤徳光さん
- 猿沢羊羹づくりに取り組む「まごころ弁当」会員の皆さんと「猿沢地区振興会」まちづくり委員会の皆さん
- 吉田惠子さん
- 若山義典さん
- 金野和則さん
- 佐藤公一さん
- 小野寺義成さん、小野寺英雄さん
- 熊谷志江さん
- 佐藤良規さん
- ヨソモノさんいらっしゃい開催報告
- 佐藤公基さん
- 自治会長サミット開催報告
- 岩渕美央さん
- 熊谷 まき子さん
- 千田秀明さん、吉田真梨子さん
- 五十嵐正一さん
- 佐山昭助さん、佐藤甲子夫さん
- 高橋邦彦さん
- 佐藤晄僖さん
- 伊藤京子さん
- 阿部興紀さん
- 伊藤満明さん
- 小野寺篤さん
- 佐藤佑樹さん
- 小野寺威夫さん
- 小野寺秋悦さん
- 菅原幸子さん、小山亜希子さん 、菅原花さん
- 岩井確司さん
- 松元美樹さん
- 及川宏さん、岩渕力也さん
- 伊勢徳郎さん、佐藤紀子さん、熊谷光喜さん
- 鈴木 昭男さん
- 小野寺真澄さん、菅原健二さん
- 千葉智充さん
- 三浦まり江さん
- 橋本志津さん、菅原喜哉さん
- 金野馨さん、菅原敏さん、河合純子さん
- 一関市長 勝部修さん
- 二言三言【テーマ別】
- 二言三言【年代別】2021-2020
- 二言三言【年代別】2019-2017
- 二言三言【年代別】2016-2014
開館時間
9時~18時
休館日
祝祭日
年末年始
(12月29日から翌年1月3日まで)
いちのせき市民活動センター
〒021-0881
岩手県一関市大町4-29
なのはなプラザ4F
TEL:0191-26-6400
FAX:0191-26-6415
Email:center-i@tempo.ocn.ne.jp
せんまやサテライト
〒029-0803
岩手県一関市千厩町千厩字町149
TEL:0191-48-3735
FAX:0191-48-3736
X(旧:Twitter)公式アカウント
Facebook公式アカウント
LINE公式アカウント
駐車場のご案内
なのはなプラザ4Fのいちのせき市民活動センターをご利用されるお客様は、以下の有料駐車場に車を停めた場合、最大3時間まで料金が無料になります。
当センターご利用の際に駐車場無料券を発行しますので、詳しくは窓口までお問合せください。
1. なのはなプラザ駐車場(無料)
2. 一関市立一関図書館(無料)
3. 地主町駐車場
4. 一ノ関駅西口南駐車場
5. 一ノ関駅西口北駐車場
6. なの花AB駐車場
7. 大町なかパーキング
8. マルシメ駐車場