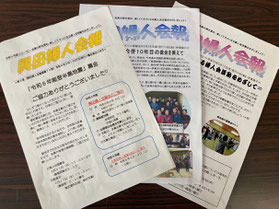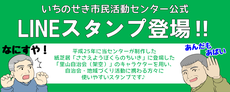※お願い※
記事内の写真や資料は、当情報誌での使用について許可をいただいて掲載しております。
無断での転載などの二次利用はご遠慮ください。
興田婦人会
(idea 2025年5月号掲載)※掲載当時と現在では情報が変わっている可能性があります。
忘年会での集合写真(令和6年12月15日)
基本情報
戦後、地区単位で組織していた全戸加入の婦人会を束ねる組織「興田婦人連合会」が前身。平成22年に組織改革を行い、任意加入の興田婦人会が誕生。現在の会員数は42名。令和6年一関市市民憲章推進大会において長年の活動実績が表彰された。
※問い合わせは一関市興田市民センターへ
◆TEL:0191-74-2201
絆を深め、楽しくタメになる活動の継続を
当時の先生がつづる 婦人会と地域
平成22年に発足した大東町興田地域の「興田婦人会」ですが、歴史を辿ると、戦前から地区単位(旧小学校区単位=京津畑、丑石、中川、天狗田、興田)で地区婦人会(以下、単婦)を組織しており、戦後は、全戸加入で生活必需品の受注のお世話などを行っていました。そんな中、「興田地域として単婦活動の情報共有の場を」という声から、昭和30年に単婦の連合組織「興田婦人連合会(以下、興婦連)」を発足。これが、現興田婦人会の前身となっています。
「婦人会には長い歴史があるんです。昭和30年代の婦人会の様子は実際に見たわけではありませんが、当時の婦人会活動は地元にとても密着した活動だったようです」と語るのは、興田婦人会の現会長・及川洋子さんです。中川小学校(当時)の先生から頂いた手紙に記されていたという「中川婦人会(単婦の一つ)」の様子を紹介してくれました。
「特に面白いなと感じるのは、婦人会事務局は学校の先生が担い、総会は小学校PTA総会と同日に開催。総会後は先生方も交えて交流会を開催していたようです。歌あり踊りありで、『総会後の交流会は地域を知る楽しみの一つだった』と記されています。交流会を機に、地域・学校・PTAが一体となって子どもたちを見守り育ててきたのでしょう」と微笑みます 。
第一変化期を乗り越えて
昭和30年に設立された興婦連は、単婦の事業(敬老会での踊り当番のお世話、資源回収、総会や役員会等の会議など)もそれぞれ継続しつつ、平成22年までの55年という長い月日を地域と共に歩み続けてきました。
しかし、興婦連の会議や連合会事業(助産所の開所支援、高齢者施設慰問活動、新生活運動、文化祭での食堂開設等)も加わり、二重の活動で「仕事や役割が増えた」「自分たちの本来の活動ではない」と感じる人や、時代の変化で「家庭や個人の時間」を大切にする人も増え、新入会員が減り会員の高齢化が話題に。
「新生活運動等もあり、興婦連発足以降、単婦活動も興婦連も勢いがありました。会員が新しいことにどんどん挑戦し活発に活動を行ってきましたが、平成初め頃から徐々に課題が見え始めたのです。
今思えば、第一の変化期でしたね」と及川さん。平成16年には「興婦連創立50周年事業」も開催されましたが、実際、「単婦活動は続けるが興婦連からは脱退したい」という単婦からの申し入れも……。そこで、平成20年に興婦連の発展的解消を目的として「興田婦人会組織合併推進委員会」を立ち上げ、婦人会活動の今後を考え始めたのです。
地域で楽しみを持って暮らせるように
婦人会の在り方を検討し約2年後の平成22年4月、個人の意思で加入する「新興田婦人会(初代会長 菊池信子氏。発足1年目のみ、「新」をつけた)」が誕生。その前後の年で、各単婦は解散します。会員は地区毎に班を編成し、班長が理事を務める仕組みとし、「会員の絆を深め、楽しくタメになる婦人会活動をめざしましょう」をスローガンに、第二の変化を遂げます。
「継続事業として文化祭での食堂開設や高齢者施設慰問活動のほか、新たに小学校のプール清掃支援や下校見守り活動なども事業に組み入れました。そしてスローガンに掲げる『楽しくタメに』という部分から3つのサークル活動(作ろう会、踊ろう会、音楽を楽しもう会)の開始と、年に一度のお楽しみ芸術鑑賞会なども企画しました」と振り返るのは、当時事務局であり二代目会長(平成26年~令和2年3月まで)を担った伊東陸子さんです。
「地域で得意な方をリーダーに活動してきた」というサークルは「私たちの活動の特徴」と他の役員も続けます。また、発足直後に発生した東日本大震災以後は被災地支援を継続的に行い、現在は被災地研修という形で「有事への備え」を学び地域づくりに活かしています。
令和2年4月から会長職を譲り受けた及川さんは「コロナ禍も経験し、今は少しずつ活動を再開しています。全戸加入だった時代から、現在は個人の意思となり、会員数は42名となりました。会員の高齢化もますます進んでいるのが現状で、今後は次の世代につなぐ婦人会活動の在り方を検討する必要性を感じています。第三の変化の時期ですね」と語り、「それでも、現会員が楽しくタメになる活動を取り入れ、会員同士の絆を深め元気であること、これが一番大事」と、引き継がれてきたスローガンを次の世代へと伝えていきます。
Q.あなたにとって「興田婦人会」とは?
photo gallery
- idea 2025
- 過去の情報紙idea(PDFデータ)
- 団体紹介
- 興田婦人会
- 達古袋神楽
- むろね山野草の会
- 一関まちづくりの会
- せんまや逸品の会
- サンイチ三味線
- かわさきにあつマルシェ
- はずみ会
- おはなしと影絵劇の会 野の花
- 陶芸クラブkirameki
- 東山郷福餅つき隊
- 磐清水バスケットボールクラブ「TEAM WATANABE(チームワタナベ)」
- NPO法人奏楽のたね
- いちのせきハラミ焼なじょったべ隊
- 染色の会
- NPO法人一関文化会議所
- 渋民伊勢神楽保存会
- 還過爺+αバンド
- NPO法人 アートで明るぐ生ぎるかわさき
- アラトプロジェクト
- 一関マジックの会
- 千厩金管バンドクラブ
- オカリナサークル ハピネス
- 夏川神楽保存会
- いちのせき語り部の会
- 室根バレーボール協会
- 高橋東皐顕彰会
- 老松大黒舞保存会
- NPO法人北上川サポート協会
- 地域紹介
- 企業紹介
- 博識杜のフクロウ博士
- センターの自由研究
- 二言三言
開館時間
9時~18時
休館日
祝祭日
年末年始
(12月29日から翌年1月3日まで)
いちのせき市民活動センター
〒021-0881
岩手県一関市大町4-29
なのはなプラザ4F
TEL:0191-26-6400
FAX:0191-26-6415
Email:center-i@tempo.ocn.ne.jp
せんまやサテライト
〒029-0803
岩手県一関市千厩町千厩字町149
TEL:0191-48-3735
FAX:0191-48-3736
X(旧:Twitter)公式アカウント
Facebook公式アカウント
LINE公式アカウント
駐車場のご案内
なのはなプラザ4Fのいちのせき市民活動センターをご利用されるお客様は、以下の有料駐車場に車を停めた場合、最大3時間まで料金が無料になります。
当センターご利用の際に駐車場無料券を発行しますので、詳しくは窓口までお問合せください。
1. なのはなプラザ駐車場(無料)
2. 一関市立一関図書館(無料)
3. 地主町駐車場
4. 一ノ関駅西口南駐車場
5. 一ノ関駅西口北駐車場
6. なの花AB駐車場
7. 大町なかパーキング
8. マルシメ駐車場